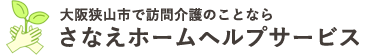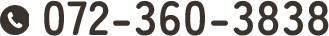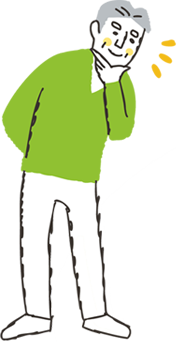2022.09.03

いつもありがとうございます。
当代表の原です。
定期的にコチラで弊社の近況や有益な情報をアップしたいのですが…、
なかなか本業の業務に忙殺されて、思う様に時間が取れていないのが現状です。
ただ単に私の段取りが悪いだけかもしれませんが… (^-^;
さて、本日はタイトルにもありますように、チーム(集団)で協力する際に気を付けておかないといけない ”罠” について、簡単に共有できればと思っています。
既にご存じの方もおられるかと思いますが、今回は「リンゲルマン効果」と言われる心理現象についてご紹介します。
私自身も、2人以上が関わる様な社内ルールを作成する際や、新たなルール作成の相談等を受ける際には、この「リンゲルマン効果」を常に念頭に置いて考えています。
それは、複数の人間(スタッフ)をルールで管理する必要が場合、この「リンゲルマン効果」が仕事のパフォーマンスに大きく影響を及ぼす可能性が非常に高いからです。
◆ リンゲルマン効果とは… ◆
【※ リンゲルマン効果 … マクシミリアン・リンゲルマン(フランスの心理学者)が提唱 】
会社などの集団組織における心理現象で、1人で作業する場合と比べ、人数の増加に伴って1人当たりの作業効率や遂行量が低下していく心理現象のこと。
「社会的手抜き」などと表現されることもある。
人間は1人で作業をしている時に比べて、集団での作業になると様々な心理が働き始めます。
そして、この「リンゲルマン効果」ですが…、
俗に言う ”サボり” の様な心理状態が生まれてしまうことで、1人当たりのパフォーマンスが著しく低下してしまう心理現象のことを指します。
本来であれば、多数の人間が協力し、力を合わせることで「全体のパフォーマンスは上がるはずだ」と思いますよね?
1人で作業を行うよりも、2人、3人、4人…と関わる人数が増えたいった方が、単純に作業効率はアップする様に感じます。
しかし、現実はそんな単純にはいきません。
逆に人数が増えるに従って、自然と1人が発揮する力や能力が減少してしまい、全体のパフォーマンスが低下してしまうことが往々にして起こるんですね。
これについては、リンゲルマン氏が実験した「綱引き」の例がとても分かりやすいので、ご紹介します。
【 集団心理を検証する「綱引き」実験 】

リンゲルマン氏は自身が提唱した理論を実証するため、綱引きを使った集団作業の心理を検証しました。
1人ずつ双方(1対1)で綱引きをしたときに、お互いが綱を引く力を100%とすると…、
・2人ずつ(2対2)で綱を引いたときの1人当たりの力は93%まで減少。
・3人ずつ(3対3)で綱を引いたときの1人当たりの力は85%まで減少。
・4人ずつだと77%まで減少しました。
・そして、8人になると、1人当たり49%まで減少したそうです。
リンゲルマン氏はこの実験により、人は集団になると「心理的な手抜き」が起こることを証明しました。
この「リンゲルマン効果」が働く主な要因としては、以下の様なものがあります。
■当事者意識の低下(責任感の欠如)
■集団による同調行動
■批判の回避(失敗や批判からの逃避) …などなど
私たちの身近な例であれば、集団で重い物を担ぐ作業(神輿を担いだり、引越し作業など)が分かりやすいと思います。
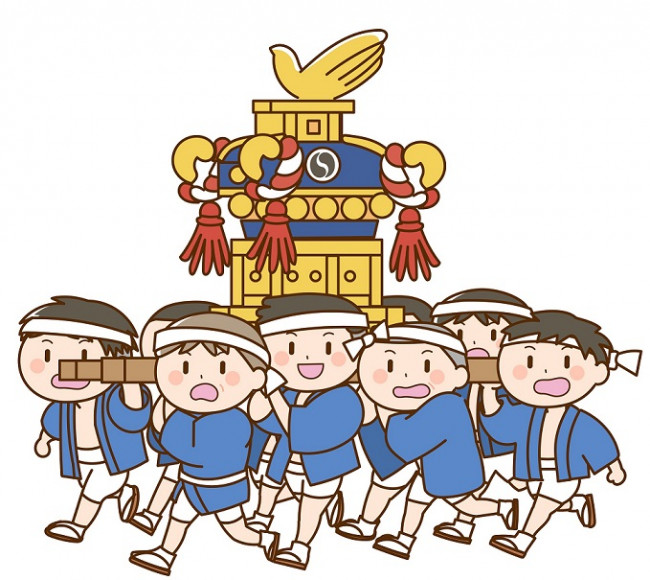
皆が協力して重い荷物を運んでいるときなど…、
・自分は全力で担いでいるつもりでも、実際にはそこまで力は入っていない。
・担いでいるフリをしながら、ちょっと力を緩めてみたりする。
皆さんも何となく経験がありませんか?
「他の人が頑張ってるから、少しぐらい自分は力を抜いても大丈夫だろう…」
という様な心理が無意識に働いて、ついつい自然と手を抜いてしまうという事が起こります。
これは、複数人が関わることによる ”当事者意識の低下(責任感の欠如)” などが大きな理由となります。
「他の人もいるから、自分はそこまで頑張らなくてもいいよね」
「自分だけじゃなく、皆の人もやってないよね」
「私だけの責任じゃないよね」といった心理状態ですね。
もう一つ、身近な例を挙げると…。
駅のホームで急に誰かが倒れたとします。
そして、その場にいるのは自分とその人だけです。
この様な場合であれば、多くの人は直ぐに倒れた人の元に駆けつけて「大丈夫ですか?」などの声掛けや救助をしようとするでしょう。

しかし、そのホームに自分以外にも多数の人がいる状態であれば、どうでしょうか?
「自分が率先して動かなくても…」
「誰かが助ける(救助する)だろう…」
「大勢の前で目立ちたくない、失敗したくない、批判されたくない…」
といった心理状態が働いて、多くの人は「お互いに顔を見回すだけで動かない(救助しない)」といった行動を取ってしまいます。
(※集団による同調行動、批判の回避・逃避などが、これに当たります)
これも立派な「リンゲルマン効果」だと言われています。

この様に、1人でなら自然に出来ていたことが、集団として集まると無意識的に自分のパフォーマンスを下げてしまうといったことが、チーム(組織)では頻回に起こります。
そのため、ルールや仕組みを作る管理者(親、上司、リーダー、先輩など)は、この「リンゲルマン効果」をしっかりと考慮たうえでルール作りをしていく必要があります。
もし、あなたがチームや組織に対して、
・何でもっと成果が上がらないんだろう…?
・何故、もっと力を合わせて協力できないんだろう…?
・全体的にサボっている様に感じるよな…。
このように悩まれているとしたら…、
チームや組織内に、この「リンゲルマン効果」という「心理的な ”手抜き”」 が働いているのかもしれません。
そして、知らず知らずのうちに、チームや組織全体における個々のパフォーマンスを低下させ、成長を鈍化させている恐れがあります。
◆ 個人と組織とのバランス ◆
集団になると「心理的な手抜き」が発生してしまい、個人のパフォーマンスが著しく下がってしまうのなら、チームで動くよりも個人レベルで個々に動いた方が良いのでしょうか?
ちなみに、私の好きな言葉のひとつに、以下の諺(ことわざ)があります。
"Fast alone、Far together"
「1人だと早く目的地まで辿り着けるが、誰かと協力すればより遠くへ辿り着ける」
1人であれば身軽ですし、自分の判断次第ですぐに物事を進めていくことができます。
(※早く目的地まで辿り着ける)
しかし、どうやっても個人レベルで成し遂げる成果には限界があります。
(※1人の人間の力だけでは、時間、労力、資金などの物理的な資源(リソース)に限りがあるためです)

一方で、組織(集団)は色々な決め事などのルール作りやその管理・運営、チームワークの構築など、周囲との連携や擦り合わせの作業や手間が膨大となります。
人間関係等のトラブルも発生しますし、全体として動き出すまでには時間が掛かります。
しかし、皆で協力し合うことが出来れば、個人レベルとは比較できない程の成果を生み出すことが可能です。
そして、より大きなゴールを手にすることが出来ます。
(※より遠くへ辿り着ける)
これは組織(集団)における圧倒的な強みです。

私はこの言葉(ことわざ)の意味自体は正しいと思っていますし、この言葉も意識しながら、常に集団の強みを模索しています。
そして同時に、集団の弱みとなる「リンゲルマン効果」も常に意識しています。
つまり、互いのバランスが重要であって、場面、状況、環境などにより、「個人レベル(少数精鋭)で動く場合」と「チームで動く場合」を使い分けることが大切であると、私は理解しています。
仕事などにおいては、何でもかんでも業務を複数人に分担させるよりは ”敢えて1人に任せる” 方が、責任感を維持しつつ明確かつ効率的な場合が意外と多くあります。
それと同時に、大きな成果(業績やゴール)を上げるためには、集団(チーム)で動く圧倒的なパワーは絶対に欠かすことはできません。
つまり、「個人」と「チーム」は共に大切であり、どちらも重要です。
その上で、会社組織やチームの強みである集団の力を着実に発揮・実践させるためにも、また個々のモチベーション低下防止や成長を加速させるためにも、管理する側の人間はチームに蔓延する「リンゲルマン効果」について、しっかりと理解しておく必要があります。
今回は非常に簡単ではありますが、私たちの集団心理に働く「リンゲルマン効果」を取り上げてみました。
多くの方が大なり小なり、何かしらのルールを作ったり運営する立場(親、上司、リーダー、先輩など)にあると思います。
今回の内容が、パフォーマンやモチベーションの低下を防ぎ、目指すゴール達成に向けてのキッカケや参考になれば幸いです。
それでは、また!

「皆で協力していこう」の罠

いつもありがとうございます。
当代表の原です。
定期的にコチラで弊社の近況や有益な情報をアップしたいのですが…、
なかなか本業の業務に忙殺されて、思う様に時間が取れていないのが現状です。
ただ単に私の段取りが悪いだけかもしれませんが… (^-^;
さて、本日はタイトルにもありますように、チーム(集団)で協力する際に気を付けておかないといけない ”罠” について、簡単に共有できればと思っています。
既にご存じの方もおられるかと思いますが、今回は「リンゲルマン効果」と言われる心理現象についてご紹介します。
私自身も、2人以上が関わる様な社内ルールを作成する際や、新たなルール作成の相談等を受ける際には、この「リンゲルマン効果」を常に念頭に置いて考えています。
それは、複数の人間(スタッフ)をルールで管理する必要が場合、この「リンゲルマン効果」が仕事のパフォーマンスに大きく影響を及ぼす可能性が非常に高いからです。
◆ リンゲルマン効果とは… ◆
【※ リンゲルマン効果 … マクシミリアン・リンゲルマン(フランスの心理学者)が提唱 】
会社などの集団組織における心理現象で、1人で作業する場合と比べ、人数の増加に伴って1人当たりの作業効率や遂行量が低下していく心理現象のこと。
「社会的手抜き」などと表現されることもある。
人間は1人で作業をしている時に比べて、集団での作業になると様々な心理が働き始めます。
そして、この「リンゲルマン効果」ですが…、
俗に言う ”サボり” の様な心理状態が生まれてしまうことで、1人当たりのパフォーマンスが著しく低下してしまう心理現象のことを指します。
本来であれば、多数の人間が協力し、力を合わせることで「全体のパフォーマンスは上がるはずだ」と思いますよね?
1人で作業を行うよりも、2人、3人、4人…と関わる人数が増えたいった方が、単純に作業効率はアップする様に感じます。
しかし、現実はそんな単純にはいきません。
逆に人数が増えるに従って、自然と1人が発揮する力や能力が減少してしまい、全体のパフォーマンスが低下してしまうことが往々にして起こるんですね。
これについては、リンゲルマン氏が実験した「綱引き」の例がとても分かりやすいので、ご紹介します。
【 集団心理を検証する「綱引き」実験 】

リンゲルマン氏は自身が提唱した理論を実証するため、綱引きを使った集団作業の心理を検証しました。
1人ずつ双方(1対1)で綱引きをしたときに、お互いが綱を引く力を100%とすると…、
・2人ずつ(2対2)で綱を引いたときの1人当たりの力は93%まで減少。
・3人ずつ(3対3)で綱を引いたときの1人当たりの力は85%まで減少。
・4人ずつだと77%まで減少しました。
・そして、8人になると、1人当たり49%まで減少したそうです。
リンゲルマン氏はこの実験により、人は集団になると「心理的な手抜き」が起こることを証明しました。
この「リンゲルマン効果」が働く主な要因としては、以下の様なものがあります。
■当事者意識の低下(責任感の欠如)
■集団による同調行動
■批判の回避(失敗や批判からの逃避) …などなど
私たちの身近な例であれば、集団で重い物を担ぐ作業(神輿を担いだり、引越し作業など)が分かりやすいと思います。
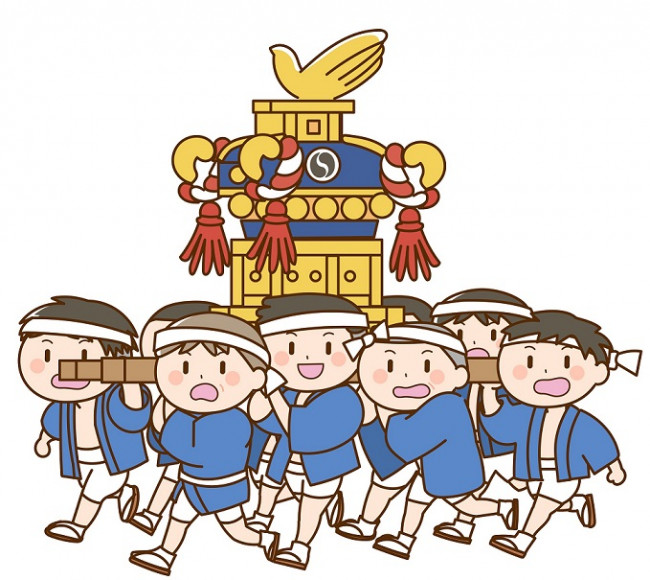
皆が協力して重い荷物を運んでいるときなど…、
・自分は全力で担いでいるつもりでも、実際にはそこまで力は入っていない。
・担いでいるフリをしながら、ちょっと力を緩めてみたりする。
皆さんも何となく経験がありませんか?
「他の人が頑張ってるから、少しぐらい自分は力を抜いても大丈夫だろう…」
という様な心理が無意識に働いて、ついつい自然と手を抜いてしまうという事が起こります。
これは、複数人が関わることによる ”当事者意識の低下(責任感の欠如)” などが大きな理由となります。
「他の人もいるから、自分はそこまで頑張らなくてもいいよね」
「自分だけじゃなく、皆の人もやってないよね」
「私だけの責任じゃないよね」といった心理状態ですね。
もう一つ、身近な例を挙げると…。
駅のホームで急に誰かが倒れたとします。
そして、その場にいるのは自分とその人だけです。
この様な場合であれば、多くの人は直ぐに倒れた人の元に駆けつけて「大丈夫ですか?」などの声掛けや救助をしようとするでしょう。

しかし、そのホームに自分以外にも多数の人がいる状態であれば、どうでしょうか?
「自分が率先して動かなくても…」
「誰かが助ける(救助する)だろう…」
「大勢の前で目立ちたくない、失敗したくない、批判されたくない…」
といった心理状態が働いて、多くの人は「お互いに顔を見回すだけで動かない(救助しない)」といった行動を取ってしまいます。
(※集団による同調行動、批判の回避・逃避などが、これに当たります)
これも立派な「リンゲルマン効果」だと言われています。

この様に、1人でなら自然に出来ていたことが、集団として集まると無意識的に自分のパフォーマンスを下げてしまうといったことが、チーム(組織)では頻回に起こります。
そのため、ルールや仕組みを作る管理者(親、上司、リーダー、先輩など)は、この「リンゲルマン効果」をしっかりと考慮たうえでルール作りをしていく必要があります。
もし、あなたがチームや組織に対して、
・何でもっと成果が上がらないんだろう…?
・何故、もっと力を合わせて協力できないんだろう…?
・全体的にサボっている様に感じるよな…。
このように悩まれているとしたら…、
チームや組織内に、この「リンゲルマン効果」という「心理的な ”手抜き”」 が働いているのかもしれません。
そして、知らず知らずのうちに、チームや組織全体における個々のパフォーマンスを低下させ、成長を鈍化させている恐れがあります。
◆ 個人と組織とのバランス ◆
集団になると「心理的な手抜き」が発生してしまい、個人のパフォーマンスが著しく下がってしまうのなら、チームで動くよりも個人レベルで個々に動いた方が良いのでしょうか?
ちなみに、私の好きな言葉のひとつに、以下の諺(ことわざ)があります。
"Fast alone、Far together"
「1人だと早く目的地まで辿り着けるが、誰かと協力すればより遠くへ辿り着ける」
1人であれば身軽ですし、自分の判断次第ですぐに物事を進めていくことができます。
(※早く目的地まで辿り着ける)
しかし、どうやっても個人レベルで成し遂げる成果には限界があります。
(※1人の人間の力だけでは、時間、労力、資金などの物理的な資源(リソース)に限りがあるためです)

一方で、組織(集団)は色々な決め事などのルール作りやその管理・運営、チームワークの構築など、周囲との連携や擦り合わせの作業や手間が膨大となります。
人間関係等のトラブルも発生しますし、全体として動き出すまでには時間が掛かります。
しかし、皆で協力し合うことが出来れば、個人レベルとは比較できない程の成果を生み出すことが可能です。
そして、より大きなゴールを手にすることが出来ます。
(※より遠くへ辿り着ける)
これは組織(集団)における圧倒的な強みです。

私はこの言葉(ことわざ)の意味自体は正しいと思っていますし、この言葉も意識しながら、常に集団の強みを模索しています。
そして同時に、集団の弱みとなる「リンゲルマン効果」も常に意識しています。
つまり、互いのバランスが重要であって、場面、状況、環境などにより、「個人レベル(少数精鋭)で動く場合」と「チームで動く場合」を使い分けることが大切であると、私は理解しています。
仕事などにおいては、何でもかんでも業務を複数人に分担させるよりは ”敢えて1人に任せる” 方が、責任感を維持しつつ明確かつ効率的な場合が意外と多くあります。
それと同時に、大きな成果(業績やゴール)を上げるためには、集団(チーム)で動く圧倒的なパワーは絶対に欠かすことはできません。
つまり、「個人」と「チーム」は共に大切であり、どちらも重要です。
その上で、会社組織やチームの強みである集団の力を着実に発揮・実践させるためにも、また個々のモチベーション低下防止や成長を加速させるためにも、管理する側の人間はチームに蔓延する「リンゲルマン効果」について、しっかりと理解しておく必要があります。
今回は非常に簡単ではありますが、私たちの集団心理に働く「リンゲルマン効果」を取り上げてみました。
多くの方が大なり小なり、何かしらのルールを作ったり運営する立場(親、上司、リーダー、先輩など)にあると思います。
今回の内容が、パフォーマンやモチベーションの低下を防ぎ、目指すゴール達成に向けてのキッカケや参考になれば幸いです。
それでは、また!